【正信偈を学ぶ】シリーズでは、浄土真宗の宗祖である親鸞聖人が書いた「正信念仏偈」の内容について解説しています。 日々を安らかに、人生を心豊かに感じられるような仏縁となれば幸いです。
さて今回からは、「正信偈」の「如来所以興出世」から「応信如来如実言」までの四句について、見ていきます。今回は、この四句の言葉の意味と、概要を見ていきます。そして次回以降に、この四句の心を、深く味わっていきたいと思います。
今回のテーマは、「親鸞聖人の喜び」です。それでは、さっそく見ていきましょう。
▼動画でもご覧いただけます
◆「正信偈」の偈文
ではまず、本文、書き下し文、意訳を見ていきましょう。
如来所以興出世 唯説弥陀本願海
(にょらいしょいこうしゅっせ ゆいせつみだほんがんかい)
五濁悪時群生海 応信如来如実言
(ごじょくあくじぐんじょうかい おうしんにょらいにょじつごん)
次に書き下し文です。
如来(にょらい)、世に興出(こうしゅつ)したまふゆゑは、ただ弥陀の本願海を説かんとなり。
五濁(ごじょく)悪時の群生海(ぐんじょうかい)、如来如実(にょじつ)の言(みこと)を信ずべし。
次に、この文章の意訳です。
お釈迦様が、この世にお出になられたのは、「迷い苦しむものを救う」という阿弥陀仏の願いを、我々に説き伝えてくださるためでした。
濁りに満ち、乱れ切った時代を生きる人々は、お釈迦様がお勧めくださる真実の教えを信じ、依りどころとするべきです。
◆如来所以興出世
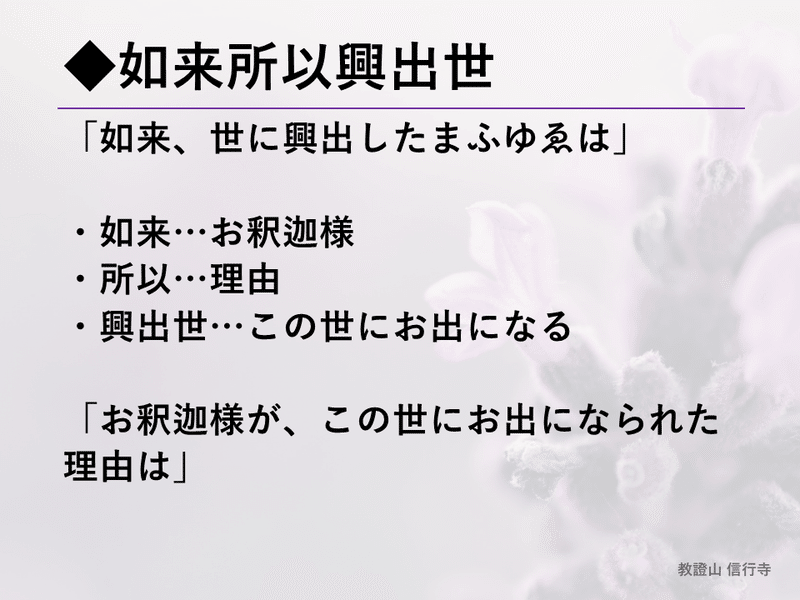
では、この四句の言葉の意味と、概要を見ていきます。お手元にお経本がある方は、是非お経本に書き込んだりしながら、ご覧いただければと思います。
まず、「如来所以興出世」という言葉をご覧ください。書き下すと、「如来、世に興出したまふゆゑは」となります。
「如来」という言葉は、仏様という意味ですが、ここでは具体的にはお釈迦様のことを指しています。様々な仏様のことを指しているという見方もありますが、ここではお釈迦様ということで話を進めます。
「所以」とは、理由という意味です。そして「興出世」とは、この世にお出になる、この世にお生まれになるという意味です。
ですので、「如来所以興出世」という言葉を直訳すると、「お釈迦様が、この世にお出になられた理由は」という意味になります。
◆唯説弥陀本願海
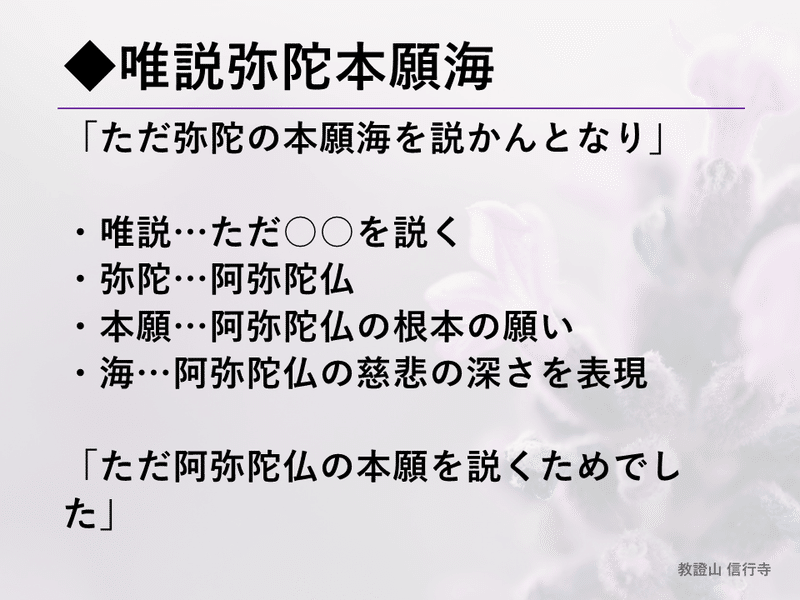
次に、「唯説弥陀本願海」という言葉を見てみましょう。書き下すと、「ただ弥陀の本願海を説かんとなり」となります。
「唯説」とは、ただ何々を説くという言葉です。お釈迦様がこの世にお出になられたのは、ただ何々を説くためだった。前の文章を受けて読むと、そういう意味になります。
では、お釈迦様がこの世にお出になられたのは、何を説くためだったかというと、「弥陀の本願海」とありますね。
「弥陀」とは、阿弥陀仏のことです。「本願」とは、「正信偈」でこれまでも出てきましたが、阿弥陀仏の根本の願いのことです。「迷い苦しむものを救う」という阿弥陀仏の願いのことです。
ここでは、「本願」に「海」という言葉をつけて、「本願海」となっています。この海という言葉にはどういう意味があるかというと、「迷い苦しむものを救う」という阿弥陀仏の慈悲の深さを、海という言葉で表現されていると言われます。
「唯説弥陀本願海」という言葉を直訳すると、「ただ阿弥陀仏の本願を説くためでした」という意味になります。
前の文章も含めて直訳すると、「お釈迦様がこの世にお出になられた理由は、ただ阿弥陀仏の本願を説くためでした」となります。
最初に読んだ意訳では、この部分をこのように訳しました。
お釈迦様が、この世にお出になられたのは、「迷い苦しむものを救う」という阿弥陀仏の願いを、我々に説き伝えてくださるためでした。
仏教の開祖であるお釈迦様が、この世にお出になられたのは、阿弥陀仏の願い、阿弥陀仏の慈悲の心を、私たち、この私に伝えるためだった。そのような親鸞聖人の受け止めが、ここには記されています。
親鸞聖人は、様々な仏道修行に励んでみても、いっこうに仏のさとりをひらきようのない自分自身に悩み苦しんでおられました。しかし、お念仏の教えに出遇い、さとりへの道がひらかれていくことを実感されます。
お念仏の教えとは、煩悩を抱えたままで阿弥陀仏に救われ、仏のさとりをひらいていくという教えであった。迷いや悩み深きもののために、自らの力では迷いから抜け出しようのないもののために、お釈迦様は阿弥陀仏の救い、お念仏の教えを説かれたのだった。
親鸞聖人は、そのように受け止め、お念仏の教えとの出遇いを喜ばれます。
お釈迦様が、この世にお出になられたのは、「迷い苦しむものを救う」という阿弥陀仏の願いを、我々に説き伝えてくださるためでした。そうした喜びの心が、「如来所以興出世 唯説弥陀本願海」という言葉で表されています。
◆五濁悪時群生海
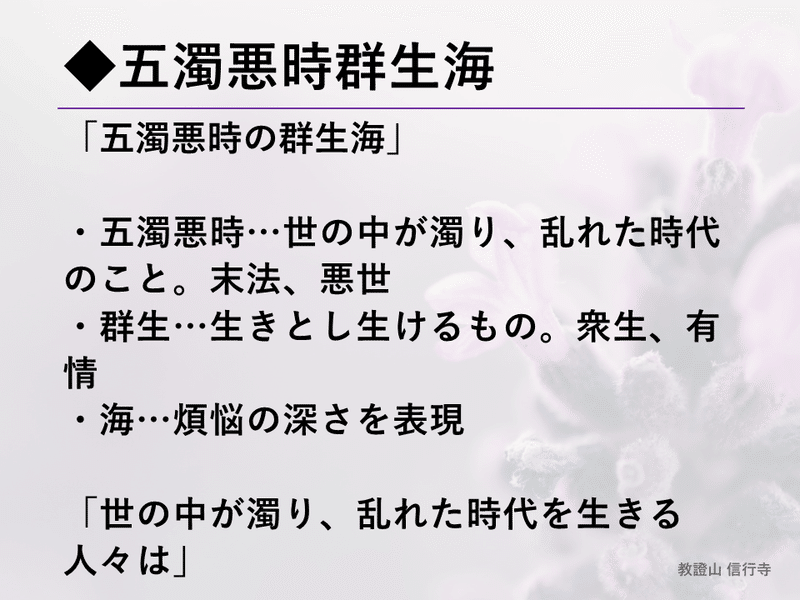
次に、「五濁悪時群生海」という言葉を見てみましょう。書き下すと、「五濁悪時の群生海」となります。
「五濁悪時」とは、世の中が濁り、乱れた時代であることを表した言葉です。末法や悪世とも言われます。
世の中が濁り、乱れた時代において、自らの力で仏道修行に励んでいくことは難しいことであること。自らの力で仏のさとりをひらいていくことは難しいことであること。「五濁悪時」という言葉には、そうした考え方や前提が含まれています。
ちなみに五濁とは、五つの濁りとあるように、具体的に五種類の濁りがあげられています。その五種類の濁りについては、別の回の時にもう少し詳しく見たいと思います。
そして、「群生海」という言葉が出てきます。「群生」とは、生きとし生けるものという意味で、衆生(しゅじょう)や有情(うじょう)とも言われます。ここでは、「群生」を人々と訳してもいいかと思います。
また、ここでも「群生」に「海」という言葉をつけて、「群生海」となっています。ここでの海とは、五濁悪時を生きる人々が抱える、貪りや怒り、迷いといった煩悩の深さを、海という言葉で表現されていると言われます。
「五濁悪時の群生海」という言葉を直訳すると、「世の中が濁り、乱れた時代を生きる人々は」という意味になります。
五濁悪時と言われる、世の中が濁り、乱れた時代において、自らの力で仏道修行に励んでいくことが難しい。自らの力で仏のさとりをひらいていくことが難しい。そういうことを、この言葉で表現されています。そして、それはそのまま、親鸞聖人がご自身の経験から実感されたことでした。
◆応信如来如実言
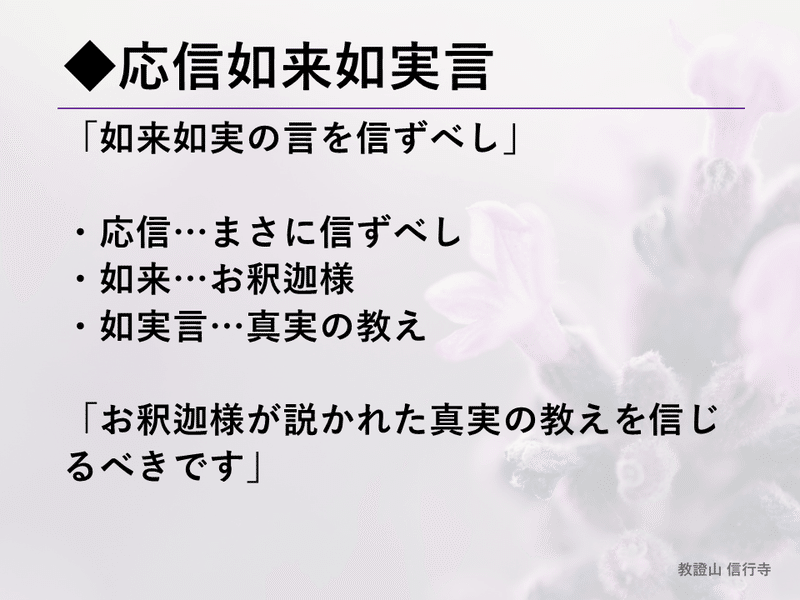
そして、「応信如来如実言」という言葉に続きます。書き下すと、「如来如実(にょじつ)の言(みこと)を信ずべし」となります。
「応信」とは、まさに信ずべしという言葉です。五濁悪時を生きる人々は、まさにこのことを信じるべきです。前の言葉を受けて、そのような意味になります。
では、何を信じるべきと書かれているかというと、その後の「如来如実の言」ですね。
「如来」とは、ここもお釈迦様のことです。そして、「如実の言」とは、真実の教えということです。「如来如実の言」で、お釈迦様が説かれた真実の教えという意味になります。
「応信如来如実言」という言葉を直訳すると、「お釈迦様が説かれた真実の教えを信じるべきです」という意味になります。
そして、お釈迦様が説かれた真実の教えとは何かというと、阿弥陀仏の救い、お念仏の教えのことであると、親鸞聖人は受け止められています。
「五濁悪時群生海 応信如来如実言」の二句の部分の意訳を、改めて見てみましょう。意訳ではこのように訳しました。
濁りに満ち、乱れ切った時代を生きる人々は、お釈迦様がお勧めくださる真実の教えを信じ、依りどころとするべきです。
繰り返しますが、親鸞聖人は様々な仏道修行に励んでみても、いっこうに仏のさとりをひらきようのない自分自身に悩み苦しんでおられました。
世の中が濁り、乱れた時代において、自らの力で仏道修行に励んでいくことが難しい。自らの力で仏のさとりをひらいていくことが難しい。親鸞聖人は、そのことをご自身の経験から深く実感された方でした。
様々な修行に励んでみても、心は散り乱れ、自身の迷いの深さに気付かされるばかり。しかし、そんな迷い苦しみの中にも、お念仏の教えに出遇い、さとりへの道がひらかれていくことを実感されます。
お念仏の教えとは、煩悩を抱えたままで阿弥陀仏に救われ、仏のさとりをひらいていくという教えであった。迷いや悩み深きもののために、自らの力では迷いから抜け出しようのないもののために、お釈迦様は阿弥陀仏の救い、お念仏の教えを説かれたのだった。
そうしたことに気付かされた時に、親鸞聖人は大きな驚きと深い喜びを感じられたことではなかったでしょうか。
そして、自らと同じように、五濁悪時とも言われる、世の中が濁りに満ち、乱れた時代を生きる人々にも、お念仏の教えに出遇い、依りどころとしてほしい。
そうした親鸞聖人の喜びの心と、お念仏の教えを依りどころとしてほしいという思いが、「五濁悪時群生海 応信如来如実言」という言葉で表されています。
そして、それはそのまま「迷い苦しむものを救う。だから私にまかせてほしい」という阿弥陀仏の願いであり、お念仏の教えに遇ってほしいというお釈迦様の勧めでもあります。
◆
いかがだったでしょうか。今回は、「如来所以興出世」から「応信如来如実言」までの四句について、言葉の意味と概要を見ていきました。
おおよその意味をおさえた上で、次回以降は、この四句の心をさらに深く味わっていきたいと思います。
合掌
福岡県糟屋郡 信行寺(浄土真宗本願寺派)
神崎修生
▼Youtube「信行寺 寺子屋チャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UCVrjoKYXFqq-CJTsAqer0_w
仏教や仏事作法について分かりやすく解説しています。
▼信行寺公式 インスタグラム
https://www.instagram.com/shingyoji.official/
信行寺の日々や行事の情報などを投稿しています。
▼前回の記事
浄土真宗【正信偈を学ぶ】第35回_成等覚証大涅槃 必至滅度願成就_生きる意味 | 信行寺 福岡県糟屋郡にある浄土真宗本願寺派のお寺 (shingyoji.jp)
■信行寺HP
https://shingyoji.jp
■Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCVrjoKYXFqq-CJTsAqer0_w
■Instagram(公式)
https://www.instagram.com/shingyoji.official/
https://www.instagram.com/shusei_kanzaki/
https://twitter.com/shingyoji1610
■TikTok
https://www.tiktok.com/@shuseikanzaki
https://www.facebook.com/shingyoji18/
■note
https://note.com/theterakoya
■LINE
https://lin.ee/53I0YnX
◇参照文献:
・『浄土真宗聖典』注釈版/浄土真宗本願寺派
https://amzn.to/2TA8xPX
・『浄土真宗聖典』七祖篇 注釈版/浄土真宗本願寺派
https://amzn.to/3CJyk9e
・『浄土真宗辞典』/浄土真宗本願寺派総合研究所
https://amzn.to/3ha42oh
・『浄土真宗聖典』浄土三部経(現代語版)/浄土真宗本願寺派
https://amzn.to/2SKcMIl
・『浄土真宗聖典』教行信証(現代語版)/浄土真宗本願寺派
https://amzn.to/3AJDXVm
・『聖典セミナー』無量寿経/稲城選恵
https://amzn.to/3htrfAV
・『正信偈の意訳と解説』/高木昭良
https://amzn.to/2SKczox
・『正信偈を読む』/霊山勝海
https://amzn.to/3yjMCvb
・『聖典セミナー』歎異抄/梯實圓
https://amzn.to/36OiRqJ
・『浄土真宗聖典』歎異抄(現代語版)/浄土真宗本願寺派
https://amzn.to/2W2WeN0
・『聖典セミナー』浄土和讃/黒田覚忍
https://amzn.to/3lYOntj
・『三帖和讃の意訳と解説』/高木昭良
https://amzn.to/3m4G3bg
・『勤行意訳本』/神崎修生
(『勤行意訳本』については、信行寺までお問い合わせください。 https://shingyoji.jp/ )
南無阿弥陀仏
